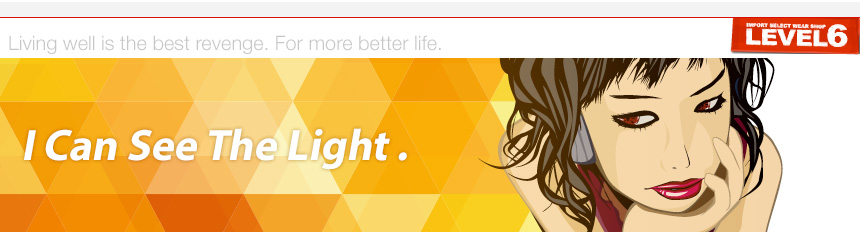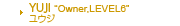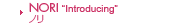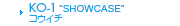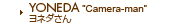TOP > どもども
LEVEL6がオープンしてからもう12年くらいですかね。あの日僕は中学生で
外から店の中のぞいたりしてたんですけども、いまやそのお店のサイト作ってるとか、
人生わかんないもんですね。ということでこんにちは。エドでっす。
なにやら福岡行ってそんまま東京行ってとかで、今は渋谷でWebデザイン。
ずっと体育部だったのにねえ、今さらデザイナーとか。はは。ほんと人生わかんない。
趣味はゲームと音楽鑑賞。音楽鑑賞はノリで30万出してCDJ購入とかしちゃって。
それまでがっつりだったクラブ通いもやめてしまいましたね。なにやらCDJ
いじくってます。好きなジャンルはディスコにガラージ。もうほんとに大好きで。
でも韓国のジャニーズ好きとあんま変わらんのかもな。ディスコへの偏愛自体は福岡にいる時
始まったんだけど、理由を考えてみたことがあってね。なんでLoft/Garage/House、つまりは
ディスコが好きなのか。その理由。それはおそらく考古学的な面白さだと思うわけです。
60年代から続いてるってのはクラブカルチャーにおいてはやはり長い歴史を誇ってると
思うけれど、俺はそのディスコの歴史を追う事も好きで、Loft/Garage/House、この3つのクラブが
作り上げた物語がものすごく好き。それはゲイというマイノリティが作った自分たちだけの
コミュニティの物語であって、華もあれば黒人ゲイの社会的抑圧、またそれが引き金となった
70年のストーンウオール暴動、さらにはコミュニティの崩壊に繋がったエイズの問題、
社会がディスコ一色になった時にロック側から出てきて、最終的に大リーグの試合中に
ディスコのレコードをスタジアム内で焼くという行動にまで発展した79年のキル・ディスコ運動など
陰の部分も併せ持っているという魅力があるわけで。
さらに黒人音楽の流れとしては重要な位置にあると思うんですよね。
現代の黒人音楽として筆頭に挙げられるであろうヒップホップはディスコをおかまだと呼んで
嫌うけれど、それはヒップホップとディスコの間に横たわるゲイとマッチョの埋められない溝な
だけであって、ヒップホップの音楽的なルーツ自体はディスコです。
何故ならオリジネイターの3人、まずクール・ハークは大量のディスコをプレイしていたし、
グランド・マスター・フラッシュはディスコDJのラジオ・ミックスから影響を受けていました。
またアフリカ・バンバータのプロダクションにはシェップ・ペティボーンとアーサー・ベイカーが
在籍していました。何よりDJバトルの鍵となった同レコード2枚掛け。
これを最初に行ったのはディスコDJのウォルター・ギボンズでした。
また普通に当時のR&Bがサンプリングされてたりしますよね、今のHIPHOP。
ただ今では70年代のそれとは全くかけ離れてしまった両者の距離、ヒップホップのシーンは
ディスコを基とし、また今でもハウスとリンクしているという音楽上のいわば「血縁」を
明かす事はないでしょう。つまりは俺たちがオリジナルだ、ということになるのかな。
ただ今のアーティスト達はそんなことを知らない人たちも多いはずですが。
エミネムはデトロイト出身なのを考えると時期的にデトロイトでシカゴ・ハウスがかかってた時期と
リンクするわけで、普通にクラブに行ってたならば、聞いていないことはおそらく無い。
そういった所でやはり馬鹿げたマッチョイズムを感じるのですが、それは俺がヒップホップを
好んで聞かない理由の一つでもあります。パフ・ダディとかはわりとそういった音楽に
理解を示してて、というかダイアナ・ロスとか使ったりね、まあハウス・プロデューサーへの
転身を計ったりとオープンにしてた部分があるよね。今の大御所ミッシー・エリオット&
ティンバランドとかは全くそんなの出してこないからね。でも彼女のキャラである"bitch"ってのは
やはりリル・キムが元祖なわけでもなく、開祖はミリー・ジャクソン。
つまり産まれはディスコなんですよね。
さて2つのジャンルの繋がりをまあこれだけかけて述べているわけですがもっと遡ると
ジャズとかそのへんのコード進行を使ってディスコ、つまりは当時のR&Bやソウル等は
形づくられていくわけですね。ディスコって言ったって、それって音楽的にはR&Bであり、
ファンクであり、ソウルであったわけで。ディスコというのは例えばアフロ・ヘアーや
ベルボトム、ホットパンツやバギーパンツみたいなファッションであったり、
キース・ヘリングのイラストやI♥NY、またスマイル・マークのようなアートであったり、
それを含めたクラブ・カルチャーおよびムーブメントを総括した呼び名です。
ただそこにはロックのような思想はなく、あるのはE、つまりはエクスタシーという当時の
ディスコに蔓延したドラッグやゲイが出会いの場として利用するといった感じの
「ただ今を貪るように楽しむ」という行為そのものを指す非生産的な享楽主義。
それは当時のロックやパンクからすると中身の無い馬鹿げた音楽でしたが、当時の社会的に
抑圧されたゲイにとっては唯一の楽しみであり、永遠のグルーヴであり、コミュニティでした。
その中で出た曲ってのは星の数ほどあるわけで、それを探して買って聞く、といった
手順を踏むのだけども、普通に聞くだけじゃないんだよね。そういったコミュニティにおいて
特別な役割を果たした曲も多いです。
例えば"weekend / phreek"はラリー・レヴァンがゲスト・ライヴの前に絶対かけていた曲
だったとか、"soul makossa / manu dibango"はデヴィッド・マンキューソが探してきて
ヒットさせた曲だとか"move your body / marshall jefferson"は
"on&on / jesse saunders"というハウスの見本のような曲を聞いて、
なんだこんなの俺でも作れるぜって思ってジェファーソンが作った曲だとか。
ひとつひとつの曲が本当に腐るほどのエピソードを抱えてる。
知れば知るほどそういった曲に対するリスペクトは深まるわけで、またそういった曲を聞くという
作業は歴史の点と点を合わせて線にしていく作業でもあって。つまりは歴史を聞いているんだなと
いうっていう感動があって、曲に対する思い入れは一層深まるわけです。その繰り返し。
それこそが俺がディスコが好きな理由であり、点と点を合わせて線にしていく、そういった意味で
考古学的な面白さがあると述べました。そしてそれは今現在のハウスやトランス、
ヒップホップを追う価値よりも大きいんですよね。
今のハウスはなんつうか、トランスの二の舞になる気がしてて。どんどんBPMも上がって、
シンセ音が目立ってて、なんだかなって思う。四つ打ちだけが唯一ルーツとして見える部分。
まあその柔軟性がハウスの全てであり、今でも生き残っている理由ではあるけれども。
トランスはそもそもインドのゴア地方の民族音楽を基にして作られた音楽で、ゴアとか
ゴア・トランスと呼ばれたりしていました。それがいつしか白人の商業主義に穢された
エピックトランスなんてのが出来上がり、今ではわけのわからん勘違いDJ、まあ僕から見れば
ですが、さすがにミッキーマウスのトランス聞いたときはびびった。そんな手合が出てきてる。
あの音楽はそもそもの基盤を忘れた、トランスの名を騙る騒音です。それは歴史の
忘却であって、冒涜なんだよってのを俺は思うんだけどそれを好んで聞いてるひとは
バックボーンがないからそんなのわからないし、またそれは知る必要がないのかも
しれないね。最終的に良いか悪いかだから。でも今のトランスなんかって歴史も底も浅くて、
知って楽しいってことが全くなくて。それよりもディスコのほうがやはりマイノリティへの興味を
捨てれない俺からすると全然思い入れが違うんですよね。
まあゴアはまだ普通に聞くけどさ。
ハウスは今現在優れたDJやリミキサー、つまりはルーツを知る作り手がきちんと大御所の
位置にいるからまだ大丈夫だと思うけどそれすらいなくなったらもう聞くことはないのかも。
クラブもroomしか行かなくなってしまいました。前はyellowとかwombとか大きいトコも行ったり
してたけどさ。もうなんか良い曲が聞けるのがここしかないっていうね。
まあハウスすら追わなくなったらひたすらクラシックスを漁ってるんだと思います。
それでもこんなに偏愛できるんだから良いんだけどね。
「メロディとコード」の時代は終わり、クラブは「音響と音質」の時代になったと
湯山玲子は「クラブカルチャー!(毎日新聞社)」で述べてました。
レイヴとかに行って身体全てを耳にしたような感覚に陥ってみるととみにその言葉の意味を
感じることは出来るけれど、別に家に帰ってテクノ買うぞとか思ったりはしない俺の嗜好ってのは
おそらくそのメロディとコードで止まってるんだと思います。
しかし90年代の渋谷族みたいなことしてんな俺。まあいいか。
ちょっと内容が突っ走りすぎてるのでこのへんで終了します(笑
ゲームのほうは。。。うーむ。まあそっちじゃ名前が売れてますくらいで(笑
みんな好きなもんが違うからね、そういうのが出るブログになると良いなと思います。
だからみんな色分けしてたりしますしね。ということでよろしくね。そんじゃ。
#posted by ED : 2006-12-18/10:13 | comment (0)